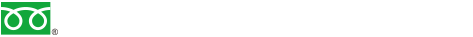遺品整理はいつから何から始める? 後悔しないための手順と進め方を解説
ご親族が亡くなられた後、深い悲しみの中で直面するのが「遺品整理」です。故人が遺した大切な品々を前に、「何から手をつけていいのか分からない」「気持ちの整理がつかず、何も手につかない」と途方に暮れてしまう方は少なくありません。
遺品整理は、単なる部屋の片付けとは異なり、ご遺族の心に寄り添いながら、法的な手続きも考慮して丁寧に進める必要があります。
この記事では、これまで数多くの遺品整理をお手伝いしてきたゼロプラスが、遺品整理を始める時期の目安から、後悔しないための具体的な進め方、そして専門業者に依頼すべきかどうかの判断基準まで、順を追って分かりやすく解説します。
1.そもそも遺品整理とは?
遺品整理とは、故人が生前に使用していた品々を整理し、片付けることです。衣類や家具といった日用品だけでなく、写真や手紙などの思い出の品、預金通帳や不動産権利書などの重要書類も含まれます。これらを「残すもの(形見分け)」「処分するもの」「貴重品」などに仕分けしていく作業全般を指します。
単なる清掃や不用品処分と違い、故人を偲び、ご遺族の気持ちを整理するための大切な時間でもあります。近年では、ご遺族の負担を軽減するため、専門知識を持ったプロの業者に依頼するケースも増えています。
2.遺品整理はいつ始めるべき?時期の目安
遺品整理を始める時期に、法律上の決まりはありません。しかし、状況によっては早めに着手すべきケースもあります。
気持ちの整理がついてからでも良いケース
故人が持ち家にお住まいだった場合など、時間的な制約がなければ、急ぐ必要はありません。葬儀や四十九日法要が終わり、ご遺族の気持ちが少し落ち着いてから、百か日や一周忌といった節目に合わせて始める方が多いようです。
早めに着手すべきケース
故人が賃貸物件(アパート・マンション、高齢者施設など)にお住まいだった場合は、注意が必要です。契約を解除しない限り家賃が発生し続けるため、できるだけ早く遺品整理を終え、退去手続きを進めるのが一般的です。
相続手続きに関わる「10ヶ月の壁」
現金や預貯金、不動産、有価証券など、金銭的価値のある遺品は「遺産」として相続税の対象となります。相続税の申告・納付期限は、原則として「故人が亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月以内」です。遺品整理が進まないと遺産の全体像が把握できないため、相続に関わる品は早めに整理に着手する必要があります。
3.後悔しない遺品整理の進め方【5つのステップ】
どこから手をつけていいか分からない、という方は、以下の5つのステップに沿って進めるとスムーズです。
ステップ1:親族への連絡と遺言書の確認
後々のトラブルを避けるため、遺品整理を始める前に関係する親族へ必ず連絡を取りましょう。「いつ、誰が中心となって行うか」「形見分けで希望する品はあるか」などを事前に話し合っておくことが大切です。また、最も重要なのが「遺言書」の有無の確認です。遺言書がある場合は、その内容が最優先されます。
ステップ2:遺品の仕分け(残す・形見分け・処分)
次に、部屋にあるものを「残すもの(貴重品・重要書類)」「形見分けで分けるもの」「処分するもの」の3つに大きく分類していきます。一つひとつ手に取ると作業が進まないため、まずは大まかに分類するのがコツです。
ステップ3:貴重品と重要書類の確保
仕分け作業の中で、以下の貴重品や重要書類は、誤って処分しないよう最優先で確保し、一箇所にまとめて保管しましょう。
- 現金、預金通帳、印鑑、有価証券、不動産権利書
- 年金手帳、保険証券、パスポート、マイナンバーカード
- 公共料金の契約書、賃貸契約書、借金の督促状など
ステップ4:デジタル遺品の整理
故人が使っていたパソコンやスマートフォンに残されたデータも「デジタル遺品」です。ネット銀行の口座やSNSアカウント、有料サービスの契約などを放置すると、トラブルの原因になります。わかる範囲で解約や退会の手続きを進めましょう。
ステップ5:不用品の処分
最後に、処分すると決めたものを片付けます。この不用品の処分が、遺品整理の中で最も時間と労力がかかる作業です。
4.不用品の処分方法と「プロに任せる」という選択肢
不用品の処分方法は、大きく分けて2つあります。
自分で処分する(行政サービスなど)
まだ使えるものはリサイクルショップに売却したり、可燃ごみ・不燃ごみ・粗大ごみなどに分別して、自治体のルールに従って処分したりする方法です。費用を安く抑えられる一方、分別や搬出に膨大な手間と時間がかかり、家電リサイクル法の対象品(テレビ、冷蔵庫など)は別途手続きが必要になります。
プロの業者に依頼する
遺品整理に対応している不用品回収業者に依頼する方法です。分別から搬出、清掃、買取、供養までを一括して任せることができます。
特に、以下のような方はプロに依頼するメリットが非常に大きいでしょう。
- 処分する遺品の量が多い
- 実家が遠方で、何度も通うことができない
- 仕事や育児で、片付けに時間を割けない
- 高齢で、重いものの搬出が体力的に難しい
- 悲しみの中で、精神的に作業を進めるのが辛い
5.まとめ
遺品整理は、ご遺族にとって精神的にも肉体的にも大きな負担となる作業です。すべてを自分たちだけでやろうと無理をして、心身の調子を崩してしまう方も少なくありません。
大切なのは、一人で抱え込まないことです。時間や人手が足りない、何から手をつけていいか分からない。そんな時は、私たちプロの力を頼ることも、故人とご自身のための一つの大切な選択です。
ゼロプラスは、遺品整理士の資格を持つスタッフが、ご遺族のお気持ちに寄り添い、故人への敬意を込めて丁寧に作業を進めます。もちろん、お見積もりは無料です。正式にご依頼いただくまで費用は一切かかりませんので、まずはお気軽にご状況をお聞かせください。