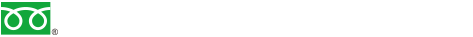遺品整理の進め方を徹底解説! 遺品整理サービスを上手に利用する方法も
遺品整理の進め方が分からずにそのまま放置していたり、計画どおりに進めることができずに困っていたりする方は多いでしょう。
遺品が多ければ多いほど事前の準備をしっかりと行い、計画を立ててから始める必要があります。しかし、実際に、どのように遺品整理を進めればいいのか、悩んでいる方は多いはずです。
そこで、本記事では、遺品整理の進め方やポイントなどを詳しく説明します。
この記事を読むことで、遺品整理を始める前の準備や、心理的な負担を軽減する方法も分かります。悩んでいる方はぜひ参考にしてください。
1.遺品整理を始める前の準備
最初に、遺品整理を始める前の準備について詳しく説明します。
故人と向き合い、心を整える
遺品整理を始める前に、故人と向き合う時間を作りましょう。遺品整理はただ遺品を整理するだけでなく、故人を偲(しの)ぶための大切な時間でもあります。故人と向き合い、心を整えることで遺品整理もスケジュールどおりに進めることができるでしょう。逆に、故人と向き合わず、心の整理がつかないまま遺品整理を始めてしまうと挫折してしまい、中途半端な状態になる恐れがあります。故人を偲ぶためにも、まずは気持ちの整理から始めてください。
家族と話し合い、役割分担を決める
遺品整理について家族と話し合い、それぞれの役割を決めることも大事です。なかなか自分で気持ちが整理できない場合でも、家族と話し合う中で整理できることがあります。家族との話し合いでは、どのようなスケジュールで遺品整理を進めていくのか、どこを誰が担当するのかなど、具体的に決めることがポイントです。役割分担をしっかりと決めておけば、順調に遺品整理を進めることができるでしょう。
必要な道具を用意する
実際に、遺品整理を始めるために、必要な道具を用意しておきましょう。最低限、遺品整理で用意しておきたい道具は以下のとおりです。
- 段ボール
- ビニール袋・ゴミ袋
- ドライバー・ペンチ・ハサミなどの工具
- 作業服(汚れても大丈夫な服)
- マスク・手袋・スリッパ
- 手押し台車
また、自分たちで粗大ゴミを処分する場合は、軽トラックなど運搬するための車も用意しておく必要があります。遺品の量や大きさなどをチェックし、必要な道具を準備してください。
2.遺品整理の具体的な手順
ここでは、遺品整理の具体的な手順を解説します。
重要書類を別に保管しておく
最初に、遺品整理の中から重要書類を別にしておく必要があります。重要書類は相続手続きなどに必要なものなので、別にして保管しておきましょう。大切な書類だからこそ、遺品整理の途中で失くさないようにするためにも、最初にチェックしておくことが重要です。重要書類は、以下のようなものとなります。
- 通帳・預金
- 印鑑
- クレジットカード
- 有価証券(小切手・株式・債券など)
- 不動産の権利書関係
- 身分証明書(運転免許証・パスポート・マイナンバーカードなど)
- 健康保険証
- 契約関係の書類
上記のものは、別の場所に保管しておくと安心です。
必要なものと不要なものに分ける
次に、遺品を必要なものと不要なものに仕分けます。故人が大切にしていたものや、思い出の品々は手元に残しておくといいでしょう。思い出の品がたくさんある場合は、「段ボール1箱分だけ残す」というルールを設けることが大切です。すべてを残してしまうと、部屋がものでいっぱいになってしまいます。どうしても自分で判断できない場合は、一時保管ボックスを設けるといいでしょう。そして、遺品整理をある程度終えた後に、もう一度考える時間を作ります。
不用品を片付ける
不要なものに仕分けたものは、早めに片付けることが大切です。特に、大型家電や大型家具などは処分までに時間と手間がかかります。自分たちで不用品を片付ける場合は、自治体の収集スケジュールと処分方法をチェックしておきましょう。また、不用品を片付ける際は、リサイクルできるものを別にしておくこともポイントです。リサイクルできるもの、買取に出せるものがあれば、処分費用を最小限に抑えられるでしょう。
部屋をキレイに掃除する
不要なものを片付けた後は、部屋をキレイに掃除します。床にはホコリや汚れが蓄積されていると思うので、掃除機や雑巾などでキレイにしてください。長年掃除していない場所があれば、頑固な汚れが付着している可能性もあります。中性洗剤などで落とせる汚れなら構いませんが、自分たちで落とせない場合は専門業者に依頼するのも方法の1つです。
大切な遺品を整理・保管する
手元に残しておきたい大切な遺品は、丁寧に保管しておきましょう。特に、アルバム・愛用品・日記・手紙などは、故人との思い出がたくさん詰まっているはずです。ホコリや湿気が少なく、直射日光が当たらない場所に保管しておけば、そのままの状態が維持できます。また、思い出の品が多い場合は、デジタル化して保管する方法もおすすめです。
3.心理的な負担を軽減する方法
ここでは、心理的な負担を軽減する方法について詳しく説明します。
家族と相談・協力する
大切な人を亡くしたという事実はとても辛く、遺品を見るたびに思い出が蘇ってはなかなか作業を進めることができないケースもあるでしょう。少しでも心理的な負担を減らすには、家族に相談し、協力しながら遺品整理を進めることが大切です。家族が近くにいない、自分1人しか遺品整理できる人がいない場合は、親しい友人など自分のことをよく理解している人に相談しましょう。心が不安定なときには優しく寄り添ってもらったり、アドバイスをしてもらったりすることで、心の負担を減らしながら遺品整理が進められるようになります。
遺品整理業者に依頼する
自分で遺品整理ができない状態であれば、遺品整理業者に依頼する方法もあります。遺品整理業者に依頼することで、遺品整理で感じていた心理的な負担が軽減できるでしょう。自分の代わりに遺品整理を行ってくれるため、スピーディーに遺品整理が終わらせることができるほか、体力・気力という面でも楽になるメリットがあります。また、遺品整理業者の中には、不用品回収サービスを行っているところもあるので、遺品の処分も任せられるでしょう。
遺品整理士が在籍している業者を選ぶ
どの遺品整理業者に依頼すべきか分からずに悩んでいる方は、遺品整理士が在籍している業者を選んでください。遺品整理士とは、遺品に関して知識を持つ専門家です。遺品の扱い方はもちろんのこと、正しい処理の方法も把握しているため、安心して遺品整理を任せることができます。遺品整理業者の需要が高まってきている昨今、悪徳業者とのトラブルが増えているので注意が必要です。遺品整理士が在籍しているのはもちろん、以下のポイントにも注目して遺品整理業者を選ぶといいでしょう。
- 遺品整理の実績があるか
- 不用品回収や買取など、サービスが充実しているか
- スタッフの対応が丁寧でスピーディーか
- 無料見積もりや無料相談を受け付けているか
- 見積書の内容が具体的に記載されているか
- 口コミや評判がいいか
上記のポイントを踏まえた上で、複数の遺品整理業者を比較してみてください。複数の遺品整理業者を比較することで、悪徳業者が見極めやすくなるでしょう。
4.ゼロプラスの遺品整理サービス
ここでは、ゼロプラスの遺品整理サービスを紹介します。
遺品整理の専門家が担当
ゼロプラスでは、遺品整理の専門家である遺品整理士が在籍しています。大切な遺品を不用品のように扱う業者も存在している中、ゼロプラスは遺品を大切に扱い、丁寧な作業を心がけている業者です。遺品の取り扱いや供養について幅広い知識を持っているからこそ、故人や遺族の意思を尊重して作業を進めていきます。遺品の扱いについて分からないことがあれば、気軽にお尋ねください。
遺品の供養や特殊清掃も
ゼロプラスでは、遺品の供養も行っています。仏壇や位牌(いはい)など、遺品の中には供養が必要なものもあるでしょう。一般的に、遺品の供養は菩提寺や近くのお寺へ依頼することになりますが、時間と手間がかかります。ゼロプラスなら遺品整理と同時に供養もできるので、スピーディーに終わらせることができるでしょう。また、特殊清掃と現状復帰工事にも対応しています。事故死や孤独死の現場作業に関しては、事件現場特殊清掃士認定を受けたスタッフが対応しているので安心です。
不用品回収・買取サービスも利用できる
不用品回収と買取サービスも利用できるのは、ゼロプラスの大きな特徴です。遺品整理業者の中には、遺品整理だけというところがあります。遺品整理で発生した不用品をゼロプラスではまとめて回収・処分できるので、自分たちでゴミを仕分ける必要はありません。また、買取可能なものがあればあるほど、処分費用の節約につながります。
徹底したリユース・リサイクルの仕組み
ゼロプラスが他社よりも低価格でサービスを提供するのは、リユースとリサイクルの仕組みを徹底しているからです。回収した不用品は自社で修理・メンテナンスをした後に再販売しています。リユースができないものは中間処理施設で分解・解体し、資源としてリサイクルしているのです。また、国内需要が低い製品は海外輸出で再利用しているため、廃棄コストを大幅に削減でき、低価格な不用品回収サービスを実現しています。
遺品整理の大まかな流れ
ゼロプラスの場合、遺品整理の大まかな流れは以下のとおりです。
- 電話またはホームページのフォームから、無料見積もりを依頼する
- 希望の日時を伝え、提示された見積書を確認する
- 見積書に納得しだい、作業日時を予約する
- 当日、スタッフが家財道具や不用品などを丁寧に整理
- 作業後、問題がなければ現金にて費用を支払う
ゼロプラスでは、万が一の際もしっかり補償できる損害賠償保険に加入済みです。スタッフが壁や床などを傷つけたとしても、責任を持って補償するので安心してください。
5.遺品整理の進め方に関してよくある質問
遺品整理の進め方に関する質問を5つピックアップしました。
Q.遺品整理を始めるタイミングはいつがいいか?
A.いつから始めるべきという決まりはないので、自分の気持ちが整理できたらで構いません。親族が一斉に集まり、ある程度時間が経過した四十九日を目安に遺品整理を始めるケースが多いようです。四十九日の法要前後であれば、遺品の分配についても話し合うことができます。そのほか、諸々の手続きを終えた後も遺品整理を始めるタイミングです。
Q.遺品整理を進める際によくあるトラブルは?
A.よくあるのは、親族間のトラブルです。たとえば、勝手に遺品整理を始めてトラブルになったり、遺産の分配で問題が起きたりする恐れがあります。遺品整理のトラブルを防ぐには、家族や相続者同士でしっかりと話し合うことが大切です。また、遺言書やエンディングノートがあれば、故人の意思を尊重する必要があります。
Q.遺品整理を上手に進めるポイントは?
A.家族で役割分担をするのはもちろん、衣類・家電・書籍・アクセサリー・食器など、カテゴリー別に仕分けることが大切なポイントです。カテゴリー別に分類することで、故人がどのようなものを持っているのか全体像が把握しやすくなります。
Q.遺品整理業者に依頼する際の注意点は?
A.どこからどこまで作業してくれるのか、遺品整理業者の作業範囲を確認することです。遺品整理業者によって、作業範囲が異なります。遺品の整理や仕分けだけを行うところもあれば、不用品回収や買取まで行ってくれる業者もあるので注意しましょう。また、見積書の内容を細部まで確認するのも注意しておきたいポイントです。
Q.遺品整理業者に依頼する際の費用相場は?
A.だいたいの費用は、下記を参考にしてください。
- 1R・1K:約5万~8万円
- 1DK・2K:約9万~12万円
- 1LDK・2DK:約13万~16万円
- 2LDK・3DK:約17万~20万円
- 3LDK・4DK:約21万~24万円
- 4LDK・5DK:約25万円~
まとめ
いかがでしたか? 遺品整理の進め方で大切なのは、最初に自分の気持ちを整理することです。心が乱れている状態で遺品整理を行うと、うまく進められずに大切な遺品を失くしてしまう可能性もあります。まずは、故人と向き合う時間を作り、心を落ち着かせるところから始めましょう。どうしても自分で気持ちの整理ができず、遺品整理が進められない場合は、遺品整理業者に依頼するのがおすすめです。ゼロプラスでは遺品整理や遺品の供養、不用品回収などさまざまなサービスを提供しているので、ぜひチェックしてください。